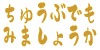| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > ショスタコーヴィチ > 作品リスト > 交響曲第6番 | ||||||||||||||||||||||||||
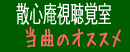 バーンスタインとVPOのタコ6。明晰で、VPOの音色も楽しむことができ、しかもバーンスタインのご多分に漏れず熱情的である。特に終楽章のスピードは、これでなくてはと思わせる。逆にいえばプレストになっていない演奏が多すぎる。 |
 Symphony No.6 in h-moll op.54 交響曲第6番 ロ短調 作品54 ■作曲 1939年 ■初演 1939.11.5 レニングラード エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団による |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
《楽器編成》
|
||||||||||||||||||||||||||
■概要 交響曲第1番以来の、紛う方なき大勝利に終わった交響曲第5番の初演から二年、同様の「あかるい人生観、生きる喜び」を吹聴する交響曲をものして更なる評判をとることなど容易だったはずのショスタコーヴィチが呈示したのは、従来の交響曲概念にひとひねりくわえた、彼らしい一癖のあるものだった。発表当時ショスタコーヴィチは「春や喜びや生命の気分をあらわそうとした」と述べているが、それが本心なのか、それとも「社会主義リアリズム」なる怪物の機嫌をとるための追従なのかは定かではない。ただ、伝えられているのは、この抒情的で特異で面白い交響曲が、当時は不評だったということだけである。 ほんらいのソナタ形式ではない、ラルゴから始まってアレグロに続き、何とプレスト楽章で終わる、という、段々速くなる「三段加速型交響曲」は、見ようによれば快速第1楽章が存在しないだけのソナタ型交響曲といえなくもないが、抒情的なラルゴ第1楽章、ソナタ形式にも変奏曲にもカテゴライズできない、うねうねとして妙に明るい第2楽章、一聴あかるいが、どうも《人生に行き詰まってヴォトカを痛飲した末の明るさ》を見せる第3楽章をみるにつけ、どうも形式的ななにを言ってもなかなか掴まえられるものではないようである。結局批評家たちはこの曲をまったく評価せず、完成から10年近くのちの1948年、いわゆるジダーノフ批判(当Web「ショスタコーヴィチ」第5部参照)において、「形式主義」の非難を浴びる。 ベートーヴェンの交響曲第4番に「エロイカ交響曲と第5番交響曲という《巨人》に挟まれた乙女」という評が定着して久しい(この評はこれで印象論的な誤りであるとわたしは思うが)けれども、当ショスタコーヴィチの第6番も、圧倒的な成功をおさめた第5番、大祖国戦争の誇りである第7番に挟まれて、一種不運な位置にある。CD録音の時代になって幸運だったのは適度な演奏時間の短さか。人気者の第5番の埋め草に丁度いい長さなので、第5番録音のカップリングとして入ることが時々ある。 世間にはもっともっと評価されていい、特異で面白い交響曲である。 ■楽章 第1楽章 ラルゴ ロ短調。4分の4拍子。しいていえば自由な三部形式。上記ショスタコーヴィチの発言に従って、この楽章を「春を描いたもの」だとする評もある。が、例えばボッティチェリが描くような春ではまったくなく、もっと間延びした、それこそシベリアの大地に控えめにコケが生えるような、春である。冒頭ヴィオラ、チェロ、木管で歌われる主題は膨らみをもっていて印象的である。あくまでも低い処から、じりじりと冬が明けていくかのようだ。木管によって歌い継がれる、中間部とおぼしきところの旋律は、冒頭主題の変容だが、葬送行進曲風である。細かなテンポ(指定)の揺動をともなっていて、情に訴えるところが強い。 第2楽章 アレグロ ト長調。8分の3拍子。スケルツォ型の三部形式か。無窮動で乱高下する木管の旋律は、聞き手に眩暈をうながすようである。中間部にも一分の隙もなく、大きな壁のようなものが踊っているようである。印象的なティンパニの独奏を挟んで、木管に主部が復帰し、滑るように終わる。 第3楽章 プレスト ロ長調。2分の2拍子。ロンド形式的で、これもまた無窮動的な性格をもっている。まず第1部、最初に出る第1主題の快活なリズムは楽章を通じて現れる。すぐ後に伸び上がって跳ねる第2主題が出て、第1主題と経過句が複雑に繰り返される。速い三拍子で何者かが踊ったのち、やがてファゴットにシンコペーションを繰り返す旋律が出るところは、ストラヴィンスキーの「春の祭典」を彷彿とさせる。コーダに入ると映画の序曲音楽のような明るさに変わり、そのままの勢いで終わる。 ■付記 全編をとおしてふらふらと浮き足だったような曲が、速いほうへ速い方へ進んで、ざくっと終わる。印象的には、快速第3楽章が終わった瞬間、何かが始まる予感がする。何かが始まらないとおかしいほどの、眩暈含みの底抜けの明るさである。しかし当然、曲はそこで終わったのだからもう何も始まらない。起こるのは、「なんだこの曲は?」という呟きと、少し困惑したような、聴衆のまばらな拍手である。ショスタコーヴィチが天才だとしたならば、聴衆の困惑までをも含めて、曲としたのかもしれぬ。一足早い、「チャンス・オペレーション(そこで偶然起こる雑音も考慮に入れた、音楽作品)」である。 大胆に想像してみると、こういうことなのかもしれぬ。第1楽章は春である。みな疲れ切っている。見よ、耕すべき大地は広大である。さいわい自分は生きている。しかしスターリンも生きている。大地は広く、そして寒い。呑まないと生きていけぬ。第2楽章。ヴォトカを呑む。眩暈がする。自分は生きている。踊り出したい気分になってきた。第3楽章。魔法の水が効いてきた。体があたたかい。さいわい自分は生きている。……「さいわい」!何という幸せな響き!さいわい!自分は!生きている!何か新しいこともじき、起こるだろう。底抜けの期待とともに、演奏は終わる。……しかし見よ、祖国がある。ソヴィエトがある。スターリンが居る。何も、変わっていない。 6番は、先にも述べたように、5番の埋め草としてCDに収録されることがある。そのようなCDに関していえば、いきおい5番終結の流れで6番を聴くことになるわけだが、5番の、ショスタコーヴィチらしさはありながらも形式的で精一杯華やかに盛り上がる曲ののちに、まるで速度を速めることを義務づけられているような(戯画的にいってしまえば、まるでショスタコーヴィチが「苦悩から歓喜へと至るなら、こんなのでいいじゃねえか!」と放言しているような)第6番を聴くにつけ、これは第5番を、(少なくとも表面的には)権力に阿る方向で作ったのちのショスタコーヴィチの、自身の音楽的良心に対する贖罪の作品なのではないかという思いを強くする。 |
||||||||||||||||||||||||||
| > 作品リストへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| > 作曲家一覧へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||