| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > ショスタコーヴィチ > 作品リスト > 交響曲第11番 | ||||||||||||||||||||||||||
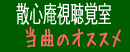 ハイティンクの交響曲第11番は国内盤も海外盤も品切れでどうにもならない。ただこの、手兵アムステルダム・コンセルトヘボウと行った11番、それから同じくACOとの13番はこのハイティンクのチクルスの中でもとてもいい。何故か西側指揮者の雄たるハイティンクがショスタコーヴィチに乗っている。ACOもいつになく調子が良い。 |
 Symphony No.11 "1905" in g-moll op.103 交響曲第11番 ト短調 《1905年》 作品103 ■作曲 1956年〜57年9月 ■初演 1957.10.30 モスクワ音楽院大ホール ラフリン指揮 ソヴィエト国立交響楽団による |
|||||||||||||||||||||||||
《楽器編成》
|
||||||||||||||||||||||||||
■概要 ショスタコーヴィチが、実際のところソヴィエト社会主義共和国連邦に如何なる想いをもっていたかということについては恐らく愛憎相半ばするところがあって本心はよくわからぬところだが、ことレニングラード、以前の都市名でいうとペテルブルグに対しての想いについては容易にわかる。戦争中のエピソードでも了解されるが、彼のレニングラードに対する愛郷心は並々ならぬものがあった。そして恐らくこの都市の歴史に対しても、そうである。 第1楽章 《宮殿前広場》 アダージョ ト短調 4分の4拍子。弱音器をつけた弦合奏により、「宮殿前広場」の旋律が流れる。寒冷な風霧が感じられる、実に見事な風景描写である。ティンパニが不気味に鳴ったのちに、トランペットのファンファーレが鳴り、宮殿の情景が繰り返されるが、中にはロシア正教聖歌もトレースされる。中間部で、ティンパニの三連符に乗る形で凍てつく風の描写とは対照的な叙情的な旋律がフルート2本で奏される。革命歌《聞いてくれ!》である。宮殿のテーマが再び流れるが、ティンパニが絶えずついてくる。小太鼓に並んで今度は先の革命歌が金管で現れる。緊張とともに変奏されたのち。次の革命歌《夜は暗い》がチェロとコントラバスに現れる。宮殿のテーマが復帰し、重々しい緊張感のなか、アタッカで第2楽章へ続く。 第2楽章 《1月9日》 アレグロ ト短調 8分の6拍子〜4分の4拍子。「血の日曜日」の楽章。第1楽章に登場したティンパニ三連符音型をベースにして主題が出る。第1部の導入は低弦に出るが、乗る主題の旋律線はショスタコーヴィチ自身の《10の詩曲》第6曲「1月9日」から引用された《皇帝我らが父よ》である。旋回する低弦はキビキビと緊張感が漂っており、警察隊を彷彿とさせる。低弦は絶えず旋回しながら旋律を展開していく。第1楽章で禍々しく出たトランペットのファンファーレが鳴り、激しく高揚したのち楽想は落ち着きを取り戻し、金管合奏で次の主題が出る。これはやはり《10の詩曲》第6曲「1月9日」から引用された《帽子をぬごう》である。主題が展開されたのち、宮殿のテーマが再登場し、民衆が宮殿に到着したことが知れる。小太鼓が三連符のリズムを鳴らす中、低弦がフガートのテーマを出す。そのテーマは各弦に引き継がれていく。一斉射撃の場面である。フルートが女子供の声を模倣する。大太鼓も砲撃を模倣する。トロンボーンのグリッサンドはサディスティックな攻撃衝動を暗示しているようだ。《帽子をぬごう》が物凄い音圧で再現される。突然音が止む。殺戮は終わった。宮殿のテーマが登場するが、すぐにトランペットのファンファーレに取って代わられる。死体が転がる宮殿前広場である。一瞬《聞いてくれ!》のテーマが出るのが悲惨の度を深める。 第3楽章 《永遠の記憶》 アダージョ ト短調 4分の4拍子。犠牲者への葬送行進曲である。第1楽章のティンパニ三連符リズムの低音旋律に乗せて、革命歌《同志は斃れぬ》が引用される。荘厳に受け渡されながら展開される。続いて金管楽器のリズム和音に乗せて、革命歌《こんにちは、自由よ》が明澄にヴァイオリンに出る。高揚する中で、前楽章の《帽子をぬごう》の旋律が煽るように現れる。葬送行進曲が再現される。 第4楽章 《警鐘》 アレグロ・ノン・トロッポ〜アレグロ ロ短調〜ト短調 4分の2拍子。金管が強烈に提示する第1主題は《圧政者らよ、激怒せよ》の革命歌である。この楽曲を通じた思いの丈をぶちまけるように激しく発展し、その中でホルンとトランペットに《帽子をぬごう》の旋律が出る。続いてマルカティッシモで弦に革命歌《ワルシャワ労働歌》が出る。トランペットが、スヴィリードフ作曲のオペレッタ《ともしび》のなかの〈雷鳴の夜はなぜつらい〉を引用する。第1楽章のファンファーレが回帰し、続いて第4楽章冒頭のテーマ、《皇帝我らが父よ》、《圧政者らよ、激怒せよ》が一斉に合流する。アダージョでは、宮殿のテーマにイングリッシュホルンが《帽子をぬごう》を重ねていく。第2楽章冒頭のテーマも断片として現れ、不安を残したままに警鐘が響き、楽章を終える。 ■付記 曲自体がひとつのソナタ形式のようになっており、第1楽章が序奏、第2楽章が主題、第3楽章が副主題的葬送行進曲、第4楽章が展開とフィナーレ、というふうになっている。 実に叙情的で、かつ情景描写的、そして何より、ショスタコーヴィチの「血の日曜日」に対する思いが非常に強く反映している名曲である。 (up: 2015.1.13) |
||||||||||||||||||||||||||
| > 作品リストへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| > 作曲家一覧へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||