| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > ショスタコーヴィチ > 作品リスト > 交響曲第1番 | ||||||||||||||||||||||||||
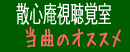 バーンスタインらしく開放感があり、しかもオケがシカゴ響でとんでもない構築力を示している。ティンパニは名手ロナルド・コスだろうか。バチッと決まっている。c/wが昔は同オケの7番で、これが超絶名演だったのだが、いまはVPOとの6番交響曲と併さっている。曲想の相性としてはむしろこちらが近いか。 爽やかデュトワの第1番。モントリオールは相変わらずオケバランスが素晴らしいが、クリ管のように凝縮しないので安心して聴ける。堅実にまとめた1枚。c/wで15番が入っているが、15番はタコさんにとって最終交響曲、自作コラージュとでもいうべき代物で、当然1番交響曲主題の引用もあるものだから、ぼうっとして聴いていると1番の次楽章かと錯覚してしまう。 |
 Symphony No.1 in f-moll op.10 交響曲第1番 ヘ短調 作品10 ■作曲 1925年 ■初演 1927.5.12 レニングラード マリコ指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団による |
|||||||||||||||||||||||||
《楽器編成》
|
||||||||||||||||||||||||||
■概要 若い頃の成功体験は、しばしば人の人生を決定する。もし19歳のショスタコーヴィチの第1交響曲初演が、あまりいい出来ではないか演奏がうまくいかないかどちらかの理由から上手くいかなかった場合、のちのショスタコーヴィチは、交響曲をあれほど量産しただろうか。……勿論、いくら万人に受けなくても作り続けた初期オペラのように、彼は……特に若い頃の彼は、思ったことをやり切る可能性はある。あるが、そもそもベートーヴェン以降の作曲家にとって、「交響曲」というジャンルは特別な代物、作曲家の魂を削る作業であり、かつ他ジャンルの活動よりも体力・精神力を消尽させる仕事であったのは自明である(ブラームスが交響曲第1番に26年を費やした、というのもその辺りに理由がある)。だからこそ、ベートーヴェン以降、大作曲家と呼ばれた人々は、その生涯において、二けたに行くか行かないかという数の交響曲を完成するに止まっている(たとえばブラームスは4曲、ブルックナーは9曲、マーラーは10曲、チャイコフスキーは6曲、シベリウスは7曲、ヴォーン・ウィリアムズも7曲)。それに比べてショスタコーヴィチは15曲もの交響曲作品を遺した。ロマン主義以降の作曲家としては異例の15曲という多数の交響曲を作り上げることができたのは、ソ連で活動したという特殊事情もさることながら、やはり交響曲第1番の成功体験も一助あってのものではなかろうか、そのような思いがある。 しかしのちの人間がそのような夢想をしてみたくなるほど、この第1交響曲の初演は見事にうまくいった。ショスタコーヴィチ自身、のちに初演日を「二番目の誕生日」と呼んだほど、彼の人生を変えたものである。 彼がこの作曲に手をつけたのが1924年。父親の死去に伴う家計逼迫のため音楽院の卒業が2年延長され、卒業制作として書かれたものである。当時ショスタコーヴィチの指導教授は、リムスキー=コルサコフ派のシテインベルクであった。彼は独特で斬新なショスタコーヴィチの第1交響曲スケルツォを見て酷評したと伝えられる。ここでざくざくカットしたり改作したりする作曲家は並のそれなのだろうが(尤もブルックナーが並の作曲家だといっているわけではないが)、そんなことをするようなショスタコーヴィチではない。ジャズ音楽的テイスト、劇伴音楽的軽妙さを存分に盛り合わせた名曲を世に問うた。そして初演の日のそれは、大喝采を浴びた。 ■楽章 第1楽章 アレグレット - アレグロ・ノン・トロッポ。トランペットの息の長いフレーズで導入部が始まる。第1主題は4分音符 - 三連符 - 4分音符変形(付点つき)の基本ユニットで構成された行進曲風のもの。ただし半音階進行で、本来の全音階的行進曲からすると奇妙な不安定さを感じる。ショスタコーヴィチの他の交響曲と同様、この第1主題ユニットおよび旋律は、最終楽章において重要な役割を果たす。 第2楽章 スケルツォ。A-B-A-B' という構成になっている。8分音符 - 16分音符*2 - 8分音符*2、という「タン・タタ・タン・タン」というリズムが基本となっている。再現部Aにてピアノが主題を奏した後の盛り上がりは、のちに映画音楽で名を馳せるショスタコーヴィチの面目躍如たるところだ。その直後、ピアノ独奏が和音を唐突に三回叩いて、それを合図として楽章を静かに終わるところなどは、まるでホルンとトランペットに主題を取られたピアノが怒って演奏をやめさせたような感じで、ハイドン的な遊びを感じさせる。 第3楽章 レント。A-B-Aの三部形式。雄大優美ではあるが非常に粘りがある楽章。その粘りは《トリスタンとイゾルデ》をも、またショスタコーヴィチ自身が後に作る第5交響曲終曲のコーダ部分、あるいは第8交響曲のやはり終曲コーダ部分をも彷彿とさせる。冒頭レントはオーボエに出るが、やはり半音階的進行で、重々しい弦の伴奏も相俟って、ゆるやかに大地がうねり上がるようだ。 第4楽章 レント - アレグロ・モルト。第1楽章断片を思わせるような木管、第3楽章の断片をチェロが奏する。アレグロ・モルトという、非常な速さで登場する主部は第1楽章主題に類似している。どんと盛り上がった後、静かな第2主題が登場する。第1主題と第2主題は対立的というよりは絡み合うようにして楽想を盛り上げていく。パッと鳴りやんでティンパニが独奏、第3主題の重苦しい半音進行的旋律が復帰する。第2主題が表情を変えて劇的に全合奏され、トロンボーンが第1主題拡大形で下支えする中、熱狂的に、しかしざっくりと全曲が終わる。 ■蛇足 調性を逸脱しようとうろうろする半音階進行、カノン、反行形、拡大形、縮小形、逆行形、突然の全休止とソロ、など、やれることを皆やってみた、というような新進気鋭の作曲家らしい作品。主題労作で展開する、というようなベートーヴェンマニアな感じはつゆほども感じさせないが、それでも尚かつ纏まりを覚えさせる、しかもショスタコーヴィチらしい独特の不気味さも感じさせる、という、さわやかな全のせ丼みたいな名曲である。タコさん本人はこの曲に満足しなかったという話も聞くが、充分だと思うね。 また、この曲に対し初見で拍手喝采した当時のサンクトペテルブルグの聴衆も凄い。さすがは帝政ロシアの首都民、批評眼は尋常ではない。ただ、この初演から65年余り、この都市の文化的蓄積はソ連文化省によって食いつぶされることになる。 (up: 2009.11.17) |
||||||||||||||||||||||||||
| > 作品リストへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| > 作曲家一覧へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||