| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > マーラー | |||
|
|||
【人間】 身体: 知力: 武力: 指揮: 魅力: 政治: 短気: 信仰: 【音楽】 楽器: 旋律: 簡潔: 構成: 雄大: 革新: 時代: |
 |
||
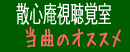 penguinのclassical rough guide。いわゆる西洋古典音楽系列と考えられる作曲家のほとんどが網羅されており、読み物としても、参照資料としても面白い。ディスクレビューも含まれている。 【DVD/映画】 ケン・ラッセル監督の問題作。基本的な感想はブログにも書いたが、非常に面白い。一番の見所は、映像が音楽にあらかじめ「負けている」処。「負けるが勝ち」を実践している。明らかに奇を衒った表現が各所に現れるが、むしろマーラーの音楽を詩的に映像化したものと捉えると、奇妙な映像に心地よさすら感じられる。一見の価値はある作品。勿論、伝記映画のつもりで見てはいけない。 音楽之友社「作曲家・人と作品」シリーズの一。マーラーを読む本というよりは著者村井翔を読む本というに近いが、一般のマーラー評に一定の距離を置いており、非常に面白い。 本文でも少し触れた、マーラー編曲のシューマン交響曲全集。1番などは冒頭から音が全く違い、非常に面白い。シューマンはよく「オーケストレーションが下手」といわれる。やはりマーラー編のが鳴りがいい。シャイーの共感と情熱に満ちた演奏も◎。 |
時代を先取るものの道は、いつの日も苦悩に満ちてある。 波を浴び、氷を砕き、苦心惨憺の末に道を切り開いたとしても、その偉業を評価すべき凡俗の他者は、彼の後ろをついて来ているがゆえにその偉大さが目に入らない。 彼が力尽き、斃れたとき初めて、後続者は目の前の厚氷を見る。 途方に暮れながら、砕氷者としての彼の巨大さに今更ながら気付く。 先人は常に、凡俗の回顧の中にのみ存在する。 ■属性 グスタフ・マーラー。 指揮者。 作曲家。 ユダヤ人。 ボヘミアン。局外者。 マキャベリスト。権力主義者。 宗教的転向者。 被姦通者。 彼には属性がある。複数ある。 このように属性を並べてみるにつけ、彼の中には、20世紀が凝縮されてあるような気がしてならない。 ■略歴 マーラーは1860年、ユダヤ系の、富裕な商家に生まれる。彼が生まれた場所はプラハとウィーンのほぼ中間にあるカリシュトである。12人家族の2番目に生まれた彼は、大作曲家のご多分に漏れずすぐに音楽的才能を発揮する。特に音楽的記憶力は卓抜たるもので、弱冠2歳余りで数百曲の民謡を記憶していたという。比較的裕福だったマーラー家は、「マーラーの音楽的才能を伸ばすため」比較的大きな都市であるイーグラウに移ることになる。  1875年、マーラーはウィーン音楽院に入学、ロベルト・フックスにピアノを、フランツ・クレンに作曲を学ぶ。ここでもまた才能を発揮し、1878年にはピアノ五重奏曲で賞を得ている。 マーラーと当代きっての著名人とのクロスオーヴァーは何度かあるが、その中でも注目すべきはブルックナーとの出会いである。当時音楽院で音楽理論を教えていたブルックナーの講義を受け、大いに感激したマーラーは、以後ブルックナーと親しく交際するようになる。また、フーゴー・ヴォルフと交流を持ったのもこの頃で、このアウトサイダー二人は互いに影響を与えあった。 まず彼は指揮者として世に出る。既に20代の前半においてオルミュッツ歌劇場、カッセル歌劇場などの指揮者を歴任し、指揮者としての手腕を認められ始めたマーラーは1885年、ライプツィヒ市立歌劇場に客演したのをきっかけにこの歌劇場の副指揮者となる。いっぽう、同年プラハにて行った演奏活動もまた支持を集め、プラハ・ドイツ歌劇場でも正指揮者扱いで迎えられることになる。 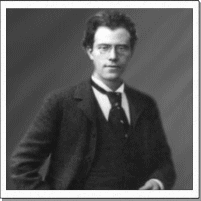 1886年、ライプツィヒに戻ったマーラーは、名指揮者アルトゥール・ニキッシュの助手となる。じつはマーラーは以前、これまた当代きっての大指揮者であるハンス・フォン・ビューローに弟子入りを志願するも受け入れられなかったという経験をもつが、このニキッシュはマーラーの才能を認め、彼らは終生の友情をはぐくむことになる。1888年には、のちの交響曲遍歴の記念すべき第1歩となる交響曲第1番 "巨人"を完成。ただし当時は交響詩扱いの全5楽章作品であった。 同年、マーラーはブダペスト王立歌劇場の音楽監督に就任する。この低迷する歌劇場に10月に赴任した彼は、その指導力および音楽性を遺憾なく発揮して音楽水準も、また経済状態も立て直す。処が歌劇場のマネージャーが替わった1891年頃から、新マネージャーであるジッヒと折り合いが悪くなり、マーラーは3月に辞職する。そしてその4月から、ハンブルク市立歌劇場のオファーを受け、正指揮者に就任する。ここでも彼は大いに力を発揮し、歌劇場の演奏水準を高めた。この歌劇場とともに、ロンドン公演など国外回りもこなしている。 1895年、マーラーの精神を苛む事件が起こる。弟オットー・マーラーの自殺である。死への想念を深めるマーラー、その精神性の始源、あるいは始源の一であるだろう。この自殺を皮切りに、彼はのち次々と近親者の不幸に出会うことになる。 ハンブルクでの指揮者生活は5年続くが、劇場支配人ポッリーニとの折り合いが悪くなり、マーラーは1897年、ウィーン宮廷歌劇場に迎えられたのを機に、ハンブルクでの地位を捨てる。「指揮者マーラー」のイメージが最も強いのはこのウィーン時代であり、彼は厳格なオケ・トレーニング能力と、濃厚で時代的な表現力をもって大活躍する。1898年以降はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団も指揮するようになり、意欲的に現代作品を演奏するとともに、多忙を極める公生活の合間を縫って作曲にも没頭、彼の中期傑作期を形成する純粋器楽曲・交響曲第5番から7番までを完成させる。先に「濃厚で時代的な表現力」と述べたが、当時の指揮者の能力を測る指標のひとつとして「編曲能力」が挙げられる。オーケストレーション理論が飽和した1900年前後、古典期の作品をそのまま演ることは余り歓迎されず、「よく鳴るように」編曲して演奏されることが常であった。編曲者としてのマーラーの能力も当然卓抜たるもので、現在でも時折、当時マーラーが編曲したベートーヴェンの合唱交響曲やシューマンの交響曲などが演奏される。 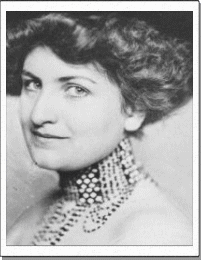 1902年、画家シントラーの娘であるアルマ・シントラー(右写真)と大恋愛の末に結婚、その頃の彼の心情は交響曲第5番、特に映画「ヴェニスに死す」にて有名になった第4楽章アダージェットに明らかである。この幸せな結婚は彼に2児をもたらすが、その二人の娘のうちの長女は1907年に死亡する。なお、彼の作品に詩人リュッケルトの作品に音楽をつけた《亡き子をしのぶ歌》があるが、これは長女が亡くなる3年も前の作品であり、直接の関係はない(しかしこの作品に没頭する彼に対し、妻アルマが「なぜそんな不幸な曲を?」と苦言を呈したという話は伝わっている)。 1902年、画家シントラーの娘であるアルマ・シントラー(右写真)と大恋愛の末に結婚、その頃の彼の心情は交響曲第5番、特に映画「ヴェニスに死す」にて有名になった第4楽章アダージェットに明らかである。この幸せな結婚は彼に2児をもたらすが、その二人の娘のうちの長女は1907年に死亡する。なお、彼の作品に詩人リュッケルトの作品に音楽をつけた《亡き子をしのぶ歌》があるが、これは長女が亡くなる3年も前の作品であり、直接の関係はない(しかしこの作品に没頭する彼に対し、妻アルマが「なぜそんな不幸な曲を?」と苦言を呈したという話は伝わっている)。1906年、作曲家としての名声もまた高まり、また多少の蓄えもでき、さらには心臓の不調を感じ始めて指揮者としての重労働よりも静かで肉体に負担をかけない作曲活動に生活の重点をおきたくなったマーラーは歌劇場の指揮者を辞め、第8番交響曲の作曲に全力を注ぐこととなる。同年、第8番が完成。この曲の初演はドイツ近辺の著名人・文化人がすべて集まったような大イヴェントとなり、生前のマーラーにとって最も成功した日として記されることとなる。 1907年、アメリカのメトロポリタン歌劇場はマーラーを、非常な好待遇にて招聘、のちの作曲活動への経済的蓄積を得たい彼はその招聘に応じる。結果として2シーズン、この地位で活動するが、肉体的変調は次第に顕わになり始めた。 これまでの大作曲家にはひとつのジンクスがあり、第9交響曲を書いたのちに没してしまう、というものがそれであった。このジンクスはベートーヴェンに始まり、シューベルト(但し現在、第9番と呼ばれていた最後の交響曲は第7番扱いとなっていて実際の「最後の交響曲」は第8番「未完成」)、ブルックナーに至るもそうであった。1908年に完成した第9番目の交響曲を彼は《大地の歌》と名付け、第9番を欠番扱い、つぎの交響曲の制作に着手する。その「迷信」はしかし結果的にマーラー個人によって拒否され、現在第9番と呼ばれる傑作をトプラッハにて、1909年に完成させる。指揮者としても、また作曲家としてもその名が高まったこの頃だが、病にむしばまれた体を抱え、また愛嬢の死、アルマの姦通にも苛まれていた彼は、安定的な精神状態とはほど遠かった。 そのまま第10番に着手した1910年、第8番をひっさげたヨーロッパ各所による演奏活動により、指揮者としての彼の名望はとどまることなく高まるが、しかし指揮活動をしながらの第10交響曲作曲は完了に至ることが許されなかった。1911年5月、ウィーンにおいて、ついにマーラーは心臓病により死亡した。 マーラーは草稿として遺ることになる第10番の原稿について、アルマに「焼却してほしい」旨遺言したという。しかし賢明にもアルマはこの稿を保管しており、われわれのもとには、完成された第1楽章および第2〜5楽章のスケッチが遺された。 + + + グスタフ・マーラー。「やがて私の時代が来る」という言葉を遺したといわれる彼。ほんの半世紀前までは、同年代の作曲家であるツェムリンスキーなどと同程度の評価であった彼の作品は、20世紀の後半に至り、遂に世界的な、また普遍的な名声を得た。どのオーケストラにおいても、シーズンのうちに彼の交響曲を演奏しないことはないといっていいだろう。彼の作品の魅力は、シェーンベルクから現代作曲家に受け継がれることになる先見性もさることながら、やはり一種の通俗性、あるいは民謡性、情緒性にある。同時に、分裂的でありながら常に感じられる統一への意志、混沌としながらもそれを超越する、一種の「昇華」へと至る常人に及びもつかぬ意志、彼マーラーが自分の作品に託したそれら意志を、20世紀を生きるわれわれは、強く欲している。われわれは「神が死んだ」ことを強く意識している。或いはより劇的な表現でいえばわれわれが「神を殺した」。にもかかわらず、上方に至るetwasを欲してやまないわれわれ。欲して止まない人々。無邪気に上方に至るetwasを信じることができた時代を懐かしく感じる。それらの人々にとって、やはりマーラーはひとつのあこがれであり、よすがであり、偶像である。 マーラーの音楽は、子供の頃の記憶のなかにしっかりとユートピアを持っている。その痕跡はあたかも、それだけのために人生は生きる価値があるのだというかのようである。けれどもこの幸福がうしなわれたものであり、うしなわれたものとしてはじめて幸福となること、その幸福とはかつて決してそうではなかったものであること、そういった意識が彼にとって同じほどに真実としてそこにある。 |
||
| > 作曲家一覧へ戻る | |||
|
|||