| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > ショスタコーヴィチ > 作品リスト > 交響曲第9番 | ||||||||||||||||||||||||||
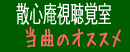 ヤンソンスとオスロ・フィルとの演奏。第9番はどの演奏を選ぶか難しい。凝縮すると曲規模が小さいだけに縮んだ焼き牡蠣みたいになってしまう。構えがデカイと諧謔が出ない。その点ヤンソンスは丹念ながら懐が深い。オスロ・フィルは有名でないが常に端正な演奏をする。オケ音色としては少し軽いが仄暗い色をもっている。その特色はこの曲についていい方に出ている。なお、ハイティンクも構えはいいがロンドン・フィルが本調子でなく、曲を消化しきれていない戸惑いが見える。 |
 Symphony No.9 in Es-dur op.70 交響曲第9番 変ホ長調 作品70 ■作曲 1945年7月〜8月30日 ■初演 1945.11.3 レニングラードフィルハーモニー大ホール エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー交響楽団による |
|||||||||||||||||||||||||
《楽器編成》
|
||||||||||||||||||||||||||
■概要 古典になるべき作品を作らねばならない時、永遠の生命をもった作品・真に人類の財産になるべき作品を創造しなければならない時がやってきた。苦しい戦争がようやく終結した時、彼は確かにこう述べた。 次は、ショスタコーヴィチにとっての第9である。 音楽愛好家にとって、もしくは作曲家にとって、1824年に作曲されたベートーヴェンの交響曲第9番以降、"9" という数字は特別なものである。大評判をとり、レニングラード市民が誇りとし、そしてスターリン賞まで受賞した交響曲第7番、そして、評価自体はその仄暗さによって高くはなかったが、その雄大さだけは大いに相通じた大編成の第8番。 次は、ショスタコーヴィチの記念碑的大作・第9番がくる。 世間はそう考えたに違いない。 そして、満を持しての1945年11月3日、ショスタコーヴィチ第9の初演。 皆、冒頭から一様に驚いた。 鳴ったのは、小編成の30分あまりの交響曲、いや、ロマン派以降の言葉でいえば交響曲というよりはディヴェルティメント、もしくはセレナード、とにかく想像していたものとは似ても似つかないものだった。合唱はもちろんないし、暗い感じでも明るい感じでもない。いや、明るいのだが、歓喜という明るさというよりは、躁状態のヨッパライが踊っているような、そんな明るさ。 ショスタコーヴィチの好意的理解者、もしくは友人たちは「生きる喜び、陽気な気分、縦横の才気、そして、辛辣さに溢れている」(ガヴリール・ポポフ)この曲を総じて好意的に受け入れた。中立的立場の人間は、これはいわば第7、第8と続いてきた戦争交響曲スケルツォなので、終楽章としての交響曲は必ず作られるだろう、といいながら困惑した。そしてそれ以外の人間は「おどけてグロテスクなユーモアを感じさせる」と評した音楽学者ネスティエフのように、まずは困惑した。 当のショスタコーヴィチは、そもそも「戦勝記念の合唱交響曲を偉大なる国民に捧げる」とまで公言していながら一体なんのつもりだったか。じつはヴァイオリン・ソナタの作曲を挟んでこの問題作を構成しはじめる1945年7月以前に、別の――恐らく雄大な――「第9」のスケッチがあったようである。しかしそのスケッチがどのようなものだったかは今となってはわからないし、実際それは破棄されてしまった。当時ショスタコーヴィチをモスクワに訪ねた友人グリークマンの証言から鑑みると、彼ショスタコーヴィチはベートーヴェンと同一のスタートラインに立ちたくなかったのではないか、という類推も成り立つ(グリークマンによるとショスタコーヴィチは当時、第9番の作曲ということで周囲が自分の曲をベートーヴェンのそれと比較するだろうことに対する戸惑いを語っている)。つまり、確信犯的に期待を膨らませておいてシニシズムの毒針で突いて破裂させる、のではなく、大きくなりすぎた期待に耐えられなくなって思わず「いなす」という振る舞いを行っているのではないかと思われることが、ショスタコーヴィチの生涯を見ていると一再ならず見られる。この第9問題に先立っては、第5で当局の信頼を回復したのちの第6での肩透かし、今回の第9についての当局に対する肘鉄砲、それからこの後にも、「レーニン交響曲をつくる」と公言しておいて期待が膨らんだ後に提供した「駄作」の第12番。特に今回の第9およびのちの第12についてはスケッチが破棄もしくは全面的に書き直された形跡があるだけに、余計にその想いを強くする。 いずれにせよ、戦勝気分まっただ中、国民的作曲家はソ連指導部を讃えるべきもしくは国民を讃えるべき、という期待があったに違いない当局の機嫌を、この曲が大いに損ねたことは疑いなく、実際にこの後ショスタコーヴィチと当局との関係は1947年の「ムラデーリ批判」および次の年初に行われる「ジダーノフ批判」によって悪化の一途をたどるのである(「ムラデーリ批判」および「ジダーノフ批判」については、当Web「ショスタコーヴィチの生涯」第5部参照)。 ■楽章 第1楽章 アレグロ 変ホ長調 2分の2拍子。スタッカートの弱音で、スキップするような第1主題が出る。ピッコロが呼応するわけだが、もうこの時点でおかしみがにじみ出ている。おもちゃの兵隊を莫迦にするような風情である。突然変ロ長調でトロンボーンが出る。ピッコロが調子はずれな鳥の声みたいな第2主題を出す。第1主題は変ホ長調にムキになったヴァイオリンで出るのだが、またトロンボーンが変ロ長調に戻す。ピッコロが同じように出てくる。展開部のヴァイオリンは随分怒っている。トロンボーンはもう4度音調の「パッパー」という変ロ長調に妄執するわけで、再現部で第1主題が出たあとに弦とトランペットとで大喧嘩みたいになるわけだけども、結局は調整役のクラリネットが第1主題を奏してなんとか終わる。 第2楽章 モデラート - アダージョ ロ短調 4分の3拍子。2部形式。クラリネットが実に寂しげな、息の長い旋律を低弦のピッツィカートに乗せて奏する。3拍子をベースに、時折4拍子の小節が挟まる変拍子が不安定さを際立たせる。中間部ではヘ短調となり、地の底から半音で沸き上がる血煙のような弦に呻き声のようなフルートがかぶさる。主部はロ短調に戻り、再度弦で湧き上がってくるものは1オクターブ上がっているだけで印象が随分違う。どちらかというと魂が迷っているようである。ホルン以外の金管は最後まで出てこない。 第3楽章 プレスト ト長調 8分の6拍子。前楽章からは雰囲気が随分変わる。スタッカートつきの順音進行的旋律がクラリネット・ソロに出る。無窮動的な旋律である。マーラーでいうと動物の葬列なわけだが、居並ぶネコやら鳥やら大きな犬やらが追いかけあいをしている風情である。やがてスペイン的なファンファーレのような旋律がトランペットに出る。次楽章、次々楽章はアタッカ(切れ目なし)でつながる。 第4楽章 ラルゴ 変ロ短調 4分の2拍子。いきなりトロンボーンとテューバという低音金管でコラールの断片みたいな音が出る。ファゴットが詠唱めいた旋律を奏した後、暗鬱な感じになって第5楽章へすぐに続く。この楽章は短い。 第5楽章 アレグレット 変ホ長調 4分の2拍子。ファゴットがふざけたような表情で息の長い旋律を少しずつ上昇し始めると第5楽章である。ヴァイオリンにその旋律は受け渡される。のちオーボエで第2主題が出る。第2主題は旅芸人の出囃子のようだ。第1主題が木管を中心に再現されるが、サーカスが始まるときのようである。中間部は第1主題を符点つきに改めて短くしたような旋律がヴァイオリンに出る。その後第1主題および第2主題はそれぞれの楽器で模倣され、大きな展開をすることなく音と参加楽器だけがだんだん大きくなっていく。やがてタンブリンを加えた凱旋行進が第1主題をベースに始まるが、どこか常に間抜けである。アレグロでスイッチが入るとシンバルやトライアングルも加わって華やかに盛り上がり始める。ただただスラプスティックになって勝手に終わる。 ■付記 この曲は、ただ漫然と聴いていると小さな佳曲あるいは珍曲ということで、頬撫でる風のように聴いてしまうのだが、正面から聴きに入ると速書きの曲であるにもかかわらず、非常に繊細に構成されているのがわかる。 全体的に「戦争勝ってよかったね!」「いいわけねえだろ!スターリン得意満面だぞ」「でもよかったね!」「よかねぇ!」みたいなのを繰り返している合間に、死者への真摯な鎮魂歌が入る、で、最後にスターリンが監視している中、やけくそになって凱旋行進をする、といった風情で、諧謔にあふれた非常に味わい深い楽曲である。 (up: 2015.1.12) |
||||||||||||||||||||||||||
| > 作品リストへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
| > 作曲家一覧へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||