| コンテンツ > 音楽 > 作曲家 > リヒャルト・シュトラウス > 薔薇の騎士 | ||||||||||||||||||||||||||
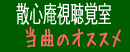  カルロス・クライバー指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団、1992年のライヴDVD。クライバーはバイエルン国立歌劇場とやった1979年のものもあるが、こちらのほうがキャストもあって端正で高貴。元帥夫人はフェリシティ・ロット。オックスははまり役クルト・モル。オクタヴィアンをアンネ・ゾフィー・フォン・オッター。ゾフィーをバーバラ・ボニーがやっている。ボニーはとても可憐だが、必要以上に高貴な魅力があってゾフィーの田舎娘っぽさが余り出ておらず、「ああこれならそりゃオクタヴィアンはゾフィー選ぶよな」と納得してしまう。フェリシティ・ロットはやや婆さん過ぎる感じに見えることが結構ある。なおこの盤はヴァルツァッキを私の好きなハインツ・ツェドニクがやっていて姿を見るのは痛快だが、喉の調子が悪いのか声は余り響かない。  上にも記載した、カルロス・クライバー指揮バイエルン国立歌劇場の79年演奏。こちらは元帥夫人をギネス・ジョーンズ、オックスをユングヴィルト、オクタヴィアンをブリギッテ・ファスベンダー、ゾフィーをルチア・ポップが演じている。若きクライバーの勢いもあり、こちらは強靭な推進力を感じる演奏。ファスベンダーは自信満々。本当は性別がどっちだったか分からんようになる。またルチア・ポップは田舎娘っぽさを存分に演じて余すところがない。最後に出てくるところなどは実に凛然としている。最後にして最大の見せ場、第3幕最後の三重唱、恐ろしいほどの美しさと三者の完璧な音響バランスを感じるのは94年盤ではなくこちら。  ベーム指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団の1969年ライヴ演奏。元帥夫人をクリスタ・ルートヴィヒ、オックスをテオ・アダム、オクタヴィアンをタチアーナ・トロヤノス、ゾフィーをエディット・マティスが演じている。ベームにしてはテンポが速めで、クライバー盤と較べてもカラヤン盤と較べても不自然さは全くない。この喜劇の浮遊感は存分に保っている。十全なキャスト、ウィーン・フィルの濃厚な音色とツボを心得た技巧、そしてリヒャルト・シュトラウスのオペラを演奏する際のベームの全能感、さらにベームのライヴ特有の熱気と夢見心地。それらが相俟って最高の名盤である。さすがベームといえども、スタジオ録音だとこうはいくまい。そしてライヴなのに完成度は異様に高く、繰り返しの鑑賞に耐えうる。あとわたしはマティスのゾフィーがとても好き。 |
▽ Richard Strauss
■作曲 1909-10年 ■初演 1911.1.26 ドレスデン ドレスデン宮廷歌劇場 エルンスト・フォン・シューフ指揮による ■台本 ホフマンスタールによる ■言語 ドイツ語 ■時代 18世紀半ば、マリア・テレジア統治時代 ■場所 ウィーン |
|||||||||||||||||||||||||
《楽器編成》
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
■概要 前作《エレクトラ》(1909)、そしてその前の《サロメ》(1905)、いずれも大迫力で、かつ革新的な音響を披露し、世界の音楽好きの耳目をいっきに集めたリヒャルト・シュトラウスだが、この《薔薇の騎士》では大きくその趣を変えている。 前二作は「悲劇」であり、かつ作曲法的にいえばワーグナー的な示導動機を盛んに用い、表現主義的な和音法を用いて作られており、有り体にいえば、そこに鳴っているのは疑いなく20世紀に入った音である。 それに比してこの《薔薇の騎士》は、「喜劇」と名付けられてもおり、ワルツをふんだんに用い、鳴る和音はその多くが協和的、いわばモーツァルト《フィガロの結婚》へのオマージュであるともいえ、耽美の作品である。ただ、《フィガロ》に寄せているからといって18世紀の音がするわけでもなく、やはりそこに鳴るのは後期ロマン派の音、ぬめぬめして巨大な、美しいが薄気味悪い、あるいは心地良い和音が響く瞬間にどこか関節を外してしまうような、やはりリヒャルト・シュトラウスらしい一癖ある、音響である。 そして何より素晴らしいのはこの作品も脚本家として大作家ホフマンスタールを得ているところで、その人心の機微を描き分ける主法は、リヒャルト・シュトラウスの絢爛たる管弦楽技法と相俟って見事な作品に結実した。 ■内容 第1幕 前奏曲 コン・モート・アジタート ホ長調 4分の4拍子。con moto (動きをつけて) agitato (激しく)、と音楽標語がついた前奏曲。急激に上昇するホルンの咆哮から始まる。たとえば《トリスタンとイゾルデ》、《ムツェンスク郡のマクベス夫人》などにも見られる、赤裸々な性交の表現である。ホルンは若々しく激しいオクタヴィアンの性的衝動、それを受ける弦などで奏される繊細な動きが経験豊かなマルシャリン。オクタヴィアンはガンガン動いてすぐに果てるような表現になっている。表現がトランクィッロ [ 静かに ] に変容したのちは、秘めやかな呼吸を示すようにヴァイオリンがゆるやかな上下降を示す。すぐに幕が開く。 第1場 元帥侯爵の邸内。元帥夫人の寝室。朝。 元帥夫人マルシャリン、そしてその愛人・17歳のオクタヴィアンが朝寝の姿で同じベッドに転がる。オクタヴィアンは若々しさもそのままに、マルシャリンが自分のものになればいいのに的なことを言う。それを優しく包容するマルシャリン。そこに足音が聞こえてくる。狩りに行っていた元帥が帰ってきたのじゃないかと二人は警戒し、マルシャリンはオクタヴィアンを物陰に隠れさせる。そこに入ってきたのはムーア人の召使い。なお、この召使いは第三幕最後にも現れ、画竜の点睛を示す。動機はアレグロ ハ長調 4分の2拍子で跳ねるようなもの。二人は胸をなでおろすが、再度来客の足音。今度はマルシャリンの従兄であるオックス男爵である。やはり夫人マルシャリンはオクタヴィアンを隠れさせる。しかししばらくして、オクタヴィアンは侍女の衣装をつけて出てくる。それを見て優しく笑うマルシャリン。オックスは野卑にかつ荒々しく部屋に入ってくる。男爵の話によると、男爵は富裕な商人であり近年叙爵されたファニナルの娘・ゾフィーと結婚することになり、相談したくやってきたとのこと。不自然ではない様子で侍女に化け、マリアンデルという偽名さえ名乗っているオクタヴィアンは幾度かこの場から離れようとするが、好色オックス男爵はかわいらしい彼(彼女)に興味を持ち下がらせない。そして、そもそも貴族の慣習で、男爵は銀製の薔薇をファニナル家に贈らなければならないので、その薔薇を持参するための「薔薇の騎士」の人選を元帥夫人に相談する。夫人はメダイヨンを取り出し、これに描かれている従弟のオクタヴィアン伯爵を、と推薦する。感謝するオックス。夫人はマリアンデルを退かせる。部屋の外では御用聞きがひしめいている。夫人は入室を許す。入室待ちをしていた鳥売り、詩人、音楽家など種々多様な人が入ってくる。彼らが騒々しくセールスを行う中、夫人は髪を結わせるが、やがて彼らが去って静かになる。孤独となった元帥夫人、ニ長調〈元帥夫人の独白〉にて自分の若き日の輝かしさを思い出すが、年齢を重ねた現在の状況、そしていつか愛するオクタヴィアンを手放さざるをえない日がくるという予感に心を重くする。 第2幕 第1場 ファニナル家。居間。 ト長調 4分の2拍子。浮き立つようなセレナード風の前奏から幕は上がる。ファニナルとゾフィー、そしてたくさんの付き人が、薔薇の騎士の到着を待っている。ゾフィーは付き人に対して、来るべき結婚への決心を素朴に、そして精一杯高踏的に語る。やがて薔薇の騎士の到着を告げる召使い。オクタヴィアンが銀の薔薇を捧げて入ってくる。オクタヴィアンはゾフィーの前に立ち、使者としての口上を述べて銀の薔薇を手渡す。〈銀の薔薇の献呈の場〉。ツィムリッヒ・ラングザーム ホ長調 4分の4拍子。オクタヴィアンはゾフィーの姿を見て、その美しさに嘆息する。ゾフィーもまたこの若者のいかにもな高貴さに惹かれる。二人対面して話をするオクタヴィアンとゾフィー。来るべき結婚のために、貴族と血筋の研究をしているという健気なゾフィー。オクタヴィアンのフルネームさえ知っているといい、そらでオクタヴィアンの長い名前を言う。「自分でも知らないのに」と喜ぶオクタヴィアン。やがて結婚相手のオックス男爵が、やはり野卑きわまりない姿で入ってくる。品定めをするかのような無作法なオックス男爵に対し、その下品さに憤るゾフィー。オックスはかまわず、猥談をしたりなどとしたい放題である。やがてオックスはファニナルに従って別室へ移る。「あんな男と結婚するのですか?」と義憤を抱くオクタヴィアン。気分のよかろうはずもないゾフィーは、オクタヴィアンと心を通じ、恋の歌を歌ってしまう。夢中の若い二人だが、後ろから男爵の手下であるヴァルツァッキとアンニーナが現れ、姦通しているとしてオクタヴィアンとゾフィーを捕らえ、大声で男爵を呼ぶ。急いで現れる男爵。義憤とゾフィーへの恋に燃える男オクタヴィアンは男爵に決闘を申し込み、そのまま斬り合いになるが、ほとんどオクタヴィアンの一人舞台、オクタヴィアンの長剣に対して腕に軽い切り傷を受けたオックスは血が出た血が出たと騒ぎ立てる。オクタヴィアンおよびゾフィー退室。大げさに手当をしてもらい、部屋に独りで座っているオックスのところにアンニーナが手紙を持ってくる。それは小姓マリアンデルからのもの。内容は、男爵さまが好きになりました、お返事おまちしています、と書いてある。あっという間に機嫌が直って「ワシと一緒なら退屈な夜はない」とワルツを歌って喜ぶ。「心づけを!」としつこいアンニーナに対し、金払いの悪い男爵は「あとでだ!」と一蹴、夢心地の男爵が自分の部屋に帰るところで幕が下りる。 第3幕 前奏曲 ヴィヴァーチェ・ポッシビレ 変ホ長調 8分の12拍子。急速で恐ろしく複雑な前奏曲を経て、第3幕はそのまま始まる。 第1場 郊外のレストラン。特別室。薄暗く、ただならぬ雰囲気である。 ヴァルツァッキが何やら、部屋のお化け屋敷的仕掛けの最終確認をしている。前幕で男爵の手下だったヴァルツァッキとアンニーナだが、男爵の金払いの悪さに愛想を尽かし、いまや完全にオクタヴィアンの配下である。オクタヴィアンは女装し、マリアンデルとして現れている。やがてオックス男爵が登場。音楽はワルツ 変ロ長調 4分の3拍子。第2幕最後、男爵が上機嫌で歌っていた旋律である。最初はマリアンデルに酒をすすめるなど得手勝手な男爵だが、やがてマリアンデルがオクタヴィアンに酷似していることに怪しみ始める。男爵、マリアンデルに迫ろうとする中、オクタヴィアンとヴァルツァッキが仕掛けたお化け屋敷的仕掛けが全開になって男爵肝をつぶす。鉦を鳴らして「誰か来てくれ、警察を呼べ」と大騒ぎ。すぐに警察官を率いて警部があらわれる。男爵を誰何した警部は、貴族のオックスだという答えを得て「証明できるか?」と問う。ヴァルツァッキがやってきていることに気づいた男爵は彼に証明を求めるが、ヴァルツァッキ知ったこっちゃないという態度。男爵怒る。一方警部は、男爵が結婚するというような話を聞き、続けて誰と結婚するのかと問う。しばらくグダグダ答えている男爵だが、遂に「ファニナルの娘とだ」と答える。同時に従者をひきつれて現れるファニナル。「急に呼び出して、なんの用ですか婿殿?」とファニナル。もちろんオクタヴィアンの差し金。警部はマリアンデルを指し、これファニナルの娘?と尋ねる。まさか!とファニナル。男爵が何処の馬の骨か分からぬ田舎娘と一緒に居るうえに、男爵の妻だと言い張る老婆やら、男爵を「パパ!パパ!」と呼ぶ大勢の子供が取り巻くのを見て、男爵の不埒な仕業を責めるファニナル。同時にゾフィー登場。当然ゾフィーはきっぱりと男爵との結婚を取り消す。それを聞いて大々的な結婚がぶちこわしになったとファニナル卒倒。既に大勢の小姓、給仕、ファニナルの使用人やら山ほど集まっている民衆たちが「ファニナル家の一大事!」と大騒ぎ。どうにもならなくなった男爵は「ほんの冗談だったんだ、ワシはこのマリアンデルと近いうち結婚するだろう」と言い出す。マリアンデルは拒絶し、警部に「伝えたいことがあるんです」と耳打ちをしてから奥の間に入っていく。そこにいとも高踏的な吹き上がるホルンとともに元帥夫人登場。男装に戻ったマリアンデルすなわちオクタヴィアン、カーテンの隙間から顔を出し、元帥夫人に「打ち合わせと違う」と困惑。しかし夫人はすべて分かったような顔をしている。男爵にいうでもなく、自分にいうでもなく「すべては茶番劇」と語る夫人。そして男爵には貴族らしく帰れと述べる。完全に姿を現すオクタヴィアン。わかったようなわからないような、という男爵、ワルツとともに去っていく。男爵を追って「勘定を!」「パパ!パパ!」「演奏代を!」とついていく給仕や取り巻きとともに男爵退場。残ったオクタヴィアンと元帥夫人、そしてゾフィー。オクタヴィアンと元帥夫人との親密な関係に気づくゾフィー、二人の女性の間でただオロオロするオクタヴィアン、そしてオクタヴィアンとの恋を諦める時期がきたことを誰よりも悟っている元帥夫人との間で、最後の、いとも美しい三重唱が始まる。なおも困惑するオクタヴィアンを、元帥夫人はゾフィーへ向かわせる。やがて抱き合うゾフィーとオクタヴィアン。やがて回復したファニナルが現れ、愛を語り合う二人を見ながら元帥夫人に「若い者はこんなもんですかな!」と上機嫌。心ここにあらずの元帥夫人はどうにか「そうね」と答える。ファニナルは元帥夫人の手を引き、先に退場。いっぽう残されたゾフィーとオクタヴィアン。抱き合って夢心地の二人。最後の二重唱が始まる。やがてゾフィーの手からハンカチが落ちるが、それに気づかず二人も手を取り合って退場。誰もいなくなった舞台にぽつんと落ちているハンカチ。やがて第1幕に出てきたムーア人の小姓が現れ、ハンカチを探して拾い、走って退場する。和音が2つ鳴って幕となる。 ■付記 オクタヴィアンは理知と高貴溢れる元帥夫人を捨て、若く素朴でやや鈍い感じのある美しいゾフィーを選ぶ。その若気の至り的な選択と、しかしそうならざるを得ない人心と、そしてそうなることを予期していた元帥夫人の思いを描きながら、その一見どこにでもあるような関係に、『昨日の世界』に描かれる、ツヴァイク的な意味での古き良きハプスブルク的社会の溶解が二重写しになるという繊細な脚本。そして、ワーグナー的な楽劇からモーツァルト・ロココへ先祖返りしたように見えながら、その実ハプスブルク最後の輝きの象徴のようなぎらぎらしたワルツを投入し、そして至る所に甘い毒のように不協和音を忍び込ませた音楽。やはりこれは時代を代表する作品だといえるだろう。 個人的には、クリムトの《パラスアテナ》の美しさと不気味さを彷彿とさせる。 (up: 2015.4.3) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| > 作曲家一覧へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||